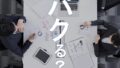キャッシュフロー計算書の作り方には「直接法」と「間接法」があります。
そして「直接法」と「間接法」の違いは1つだけです。
本記事では、キャッシュフロー計算書の「直接法」と「間接法」の違いとメリットデメリット、作り方についてご紹介いたします。
キャッシュフロー計算書の「直接法」と「間接法」の違いを知って、経営に役立つキャッシュフロー計算書を作っていきましょう!
キャッシュフロー計算書とは?

通常、決算書と聞くと「貸借対照表」と「損益計算書」を思い浮かべますが、もう一つ「キャッシュフロー計算書」というものがあります。
キャッシュフロー計算書とは、1年間や1ヶ月といった一定の期間におけるお金の流れを表すものです。
「貸借対照表」をみれば、企業の財産(資産・負債)の状況がわかり、「損益計算書」をみれば、儲かっているかどうかがわかります。
そして「キャッシュフロー計算書」では、「企業の資金がなぜ足りなくなったのか?」「儲けたお金はどこに流れたのか?」といったお金の流れがわかるようになります。
>>キャッシュフローの意味とは?簡単にわかりやすく解説します!

キャッシュフロー計算書には直接法と間接法がある

キャッシュフロー計算書の作り方には「直接法」と「間接法」があり、違いはただ1つですが、それぞれメリット・デメリットがあります。
この章では、直接法と間接法の違いとメリット・デメリットから直接法と間接法のどちらを採用するのが適しているのかをお伝えします。
直接法と間接法の違いはただ1つ!
さっそく直接法と間接法の違いについてお伝えします。
キャッシュフロー計算書の直接法と間接法の違いは「営業活動によるキャッシュフローの表示方法の違い」だけです。
まず、キャッシュフロー計算書はお金の流れを「営業活動によるキャッシュフロー」、「投資活動によるキャッシュフロー」、「財務活動によるキャッシュフロー」の3つの活動にわけてわかりやすく表示しています。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフロー

※上の画像は間接法の営業活動によるキャッシュフローの例です。
「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」のキャッシュフロー計算書の3つのお金の流れのうち、「直接法」と「間接法」が関係してくるのは「営業活動によるキャッシュフロー」のみです。
そして、「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」は「直接法」と「間接法」ともに同じ表示になります。
「営業活動によるキャッシュフロー」がどのように違うのかというと、「直接法」は営業活動によるお金の流れを営業収入、仕入、経費の支払いといった主要な取引から項目ごとに集計して作成し、「間接法」は貸借対照表・損益計算書をもとに計算して作成します。
間接法・・・貸借対照表・損益計算書をもとに計算して作成
よって、営業活動によるキャッシュフローの小計金額は「直接法」と「間接法」も同じになります。

直接法と間接法はどっちがいい?メリット・デメリットを紹介!
それでは、「直接法」と「間接法」のどちらを選択してキャッシュフロー計算書をつくるとよいのでしょうか?
「直接法」と「間接法」のメリット・デメリットについて紹介いたします。
| メリット | デメリット | |
| 直接法 | 項目ごとの収入・支出が把握しやすい | 主要な取引ごとに集計するため、手間がかかる |
| 間接法 | 貸借対照表・損益計算書をもとに作るため、手間がかからない | 税引前当期純利益から調整する為、収入・支出が把握しにくい |
直接法は項目ごとの収入・支出がわかるため、取引別のキャッシュフローが把握しやすいです。
間接法は損益計算書の税引前当期純利益から調整しているため、収入・支出の内訳がわかりませんが「営業活動によるキャッシュフローと利益がなぜズレているのか」ということは、一目瞭然にわかります。
直接法は間接法より手間がかかるため、一般的には間接法を採用される企業が多いです。ただ、国際会計基準では収入・支出が把握しやすい直接法を推奨されているので、いずれは直接法が主流になるかもしれません。
もともと中小企業ではキャッシュフロー計算書の作成義務はないのですから、自社のお金の流れを把握するためだけなら、まずは手間がかからない間接法で作成するのがベストでしょう。
直接法と間接法の営業活動によるキャッシュフローの作り方

直接法と間接法の営業活動によるキャッシュフローの作り方を紹介します。
前章でお伝えしたように、直接法と間接法の違いは「営業活動によるキャッシュフローの表示方法の違い」であり、その表示方法が違う理由は、「何を元にして作成するか?」ということです。
間接法・・・貸借対照表・損益計算書をもとに計算して作成
営業活動によるキャッシュフローの作り方【直接法の場合】
まず、直接法の営業活動によるキャッシュフローの作り方から紹介します。
直接法は「主要な取引から項目ごとに集計して作成」しますので、作り方の手順は次のようになります。
手順2:仕入による支出を集計した額を入れます
手順3:人件費による支出を集計した額を入れます
手順4:その他経費による支出を集計した額を入れます
【手順1:営業による収入を集計した額を入れます】

※現金回収は、現金化できるモノなので、預金振込や小切手回収なども含まれます。
【手順2:仕入による支出を集計した額を入れます】

※現金支払は、現金化できるモノなので、預金支払や小切手支払なども含まれます。
【手順3:人件費の支出を集計した額を入れます】

【手順4:営業費の支出を集計した額を入れます】

営業活動によるキャッシュフローの作り方【間接法の場合】
次に、間接法の営業活動によるキャッシュフローの作り方を紹介します。
間接法は「貸借対照表・損益計算書をもとに計算して作成」しますので、作り方の手順は次のようになります。
手順2:減価償却費や貸倒引当金などを調整します
手順3:営業外収益と営業外費用、特別利益と特別損失を調整します
手順4:売上債権と棚卸資産、仕入債務を調整します
【手順1:税引前当期純利益の額を入れます】

【手順2:減価償却費や貸倒引当金などを調整します】

【手順3:営業外収益と営業外費用、特別利益と特別損失を調整します】

【手順4:売上債権と棚卸資産、仕入債務を調整します】

※小計下の「営業外収入」と「営業外支出」と「法人税等の支出額」は実際に支払った金額を入れたください。例えば、未収受取利息がある場合は受取利息から未収受取利息を差し引いた金額を入れます。
キャッシュフロー計算書の全体の見方はこちらの記事が参考になります。
>>キャッシュフロー計算書の見方!ポイント3つをおさえて分析しよう!

まとめ|キャッシュフロー計算書の直接法と間接法の違いはただ1つ!

直接法と間接法の違いは「営業活動によるキャッシュフローの表示方法の違い」です。
営業活動によるキャッシュフローの表示方法が違う理由は、「何を元にして作成するか?」ということになります。
間接法・・・貸借対照表・損益計算書をもとに計算して作成
また、「直接法」と「間接法」のどちらを選択してキャッシュフロー計算書をつくるとよいのかについてメリット・デメリットを紹介いたします。
| メリット | デメリット | |
| 直接法 | 項目ごとの収入・支出が把握しやすい | 主要な取引ごとに集計するため、手間がかかる |
| 間接法 | 貸借対照表・損益計算書をもとに作るため、手間がかからない | 税引前当期純利益から調整する為、収入・支出が把握しにくい |
直接法は間接法より手間がかかるため、一般的には間接法を採用される企業が多いです。
国際会計基準では収入・支出が把握しやすい直接法を推奨されているとはいえ、もともと中小企業ではキャッシュフロー計算書の作成義務はないのですから、自社のお金の流れを把握するためだけなら、まずは手間がかからない間接法で作成するのがベストでしょう。
是非、キャッシュフロー計算書の「直接法」と「間接法」の違いを理解して、自社に合うほうを採用し、自社のお金の流れを把握するためにご活用ください。
株式会社マストップは、将来こうなりたいと目指す姿に向かっている経営者と一緒に伴走していくMAS監査事業をおこなっています。
当社が提供する経営計画サポートは、「現状を把握すること」「あるべき姿(目指す姿)を明確にすること」「全社員で共有すること」を促進し、ビジョンの達成、継続的な黒字経営を実現するための課題に取り組むことを支援することです。
まずは当社の中期5ヵ年経営計画立案サポート「将軍の日」をご利用ください。
また、「このままいくと5年後どうなる?」という課題を明確にする「あんしん未来診断」も随時行っております。
税務会計業務に長け、企業の未来をサポートすることに特化した経営支援のエキスパートによるZoom解説で、経営者の方にわかりやすくお伝えする「あんしん未来診断」もあわせてご利用ください。